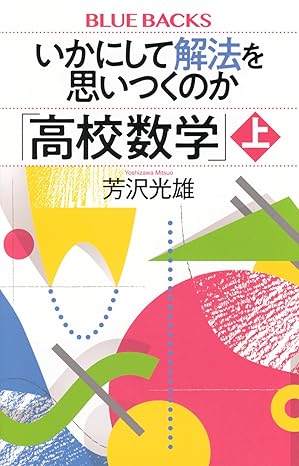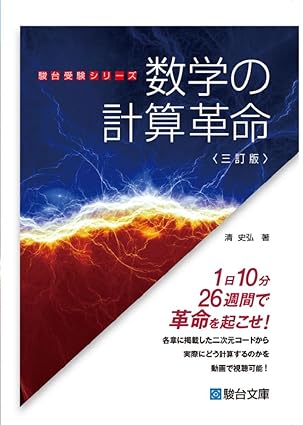平均値の定理とロルの定理の完全マスター
目次
ロルの定理とは
ロルの定理は、ある区間で連続かつ微分可能な関数について、ある条件が満たされるときに、その区間内に接線が水平な点が存在することを保証する定理です。
正式な定理の主張は以下の通りです:
ロルの定理: 関数 \( f(x) \) が閉区間 \( [a, b] \) で連続、開区間 \( (a, b) \) で微分可能であり、かつ \( f(a) = f(b) \) を満たすならば、ある \( c \in (a, b) \) が存在して、次を満たす:
\[ f'(c) = 0 \]
ロルの定理の証明と直感的理解
直感的には、「始点と終点の高さが同じなら、途中に必ず一度は水平な接線が現れる」という内容です。たとえば山を登ってまた同じ高さに戻ってくるとき、どこかで平らな場所があるというイメージです。
証明は以下のように行います:
- ① 閉区間 \( [a, b] \) で連続なので、最大値と最小値を持つ。
- ② \( f(a) = f(b) \) なので、最大値・最小値がどちらも端点でない場合、内部点で達成される。
- ③ その点では導関数が 0 になる(微分可能だから)→ よって \( f'(c) = 0 \)
平均値の定理とは
平均値の定理(ラグランジュの定理)は、ある関数の「平均的な変化率」と「瞬間的な変化率(導関数)」が一致する点が存在することを述べます。
平均値の定理: 関数 \( f(x) \) が閉区間 \( [a, b] \) で連続、開区間 \( (a, b) \) で微分可能ならば、ある \( c \in (a, b) \) が存在して、次を満たす:
\[ f'(c) = \frac{f(b) – f(a)}{b – a} \]
この右辺は「平均変化率」であり、直線的な傾きを表しています。定理は「ある瞬間、関数の接線の傾きがこの平均と一致する」というものです。
平均値の定理の証明と幾何学的意味
ロルの定理を使って平均値の定理を証明することができます。新たな関数を次のように定義します:
\[ g(x) = f(x) – \left( \frac{f(b) – f(a)}{b – a}(x – a) + f(a) \right) \]
これは、\( f(x) \) から始点と終点を結ぶ直線を引いたもので、\( g(a) = g(b) = 0 \) になります。したがってロルの定理が使え、ある \( c \in (a, b) \) で \( g'(c) = 0 \)。これを元の定義に戻せば、平均値の定理が成立します。
ロルの定理と平均値の定理の関係
ロルの定理は、平均値の定理の特別な場合と見なすことができます。平均値の定理で \( f(a) = f(b) \) のとき、右辺が 0 になり、導関数も 0 になる点がある、すなわちロルの定理となります。
具体例で理解する平均値の定理
例1:2次関数
関数 \( f(x) = x^2 \) を区間 \( [1, 3] \) で考えます。
- 平均変化率:\(\frac{f(3) – f(1)}{3 – 1} = \frac{9 – 1}{2} = 4\)
- 導関数:\( f'(x) = 2x \)
- これが 4 になる点は \( x = 2 \)。確かに \( 2 \in (1, 3) \) にある。
例2:三角関数
関数 \( f(x) = \sin x \) を区間 \( [0, \pi] \) で考えます。
- 平均変化率:\(\frac{\sin(\pi) – \sin(0)}{\pi – 0} = \frac{0 – 0}{\pi} = 0\)
- 導関数:\( f'(x) = \cos x \)
- これが 0 になる点は \( x = \frac{\pi}{2} \)。
よって、\( c = \frac{\pi}{2} \) において接線の傾きは 0、平均変化率と一致します。
まとめ
ロルの定理と平均値の定理は、微分法において重要な役割を果たす基本定理です。どちらも「導関数の性質」から関数の形状に関する深い情報を与えてくれます。
- ロルの定理は、始点と終点の値が同じなら、途中に水平な接線があることを保証
- 平均値の定理は、平均的な変化率と一致する瞬間の変化率があることを保証
- ロルの定理は平均値の定理の特別なケース
定理の理解を深めることで、より高度な微積分や解析学への土台が築かれます。数学の本質を見抜くための第一歩として、ぜひ何度も見直して理解を深めてください。