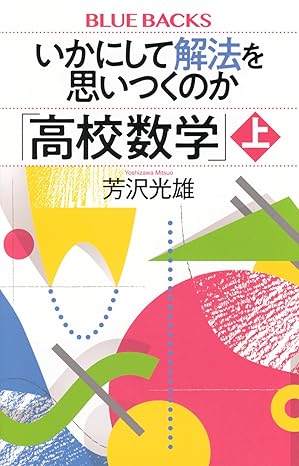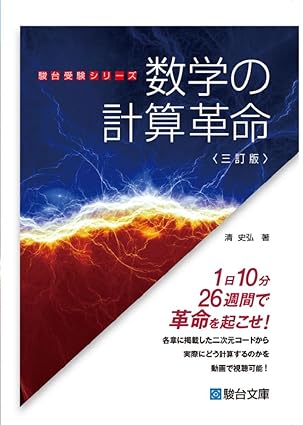テイラー展開とマクローリン展開の基礎から応用まで徹底解説
目次
テイラー展開とは
ある点 \( a \) のまわりで滑らかな関数 \( f(x) \) を、無限級数を用いて近似的に表す方法がテイラー展開です。具体的には、関数をその導関数の情報を用いて以下のように表します:
\[ f(x) = f(a) + f'(a)(x – a) + \frac{f”(a)}{2!}(x – a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x – a)^3 + \cdots \]
この級数は「テイラー級数(Taylor series)」と呼ばれ、関数 \( f(x) \) が十分に滑らか(すなわち、何回でも微分可能)であれば、元の関数と等しくなります。
マクローリン展開とは
テイラー展開の特別な場合として、展開の中心 \( a = 0 \) としたものがマクローリン展開です。つまり、以下のようになります:
\[ f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f”(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots \]
多くの基本的な関数(指数関数、三角関数、対数関数など)は、マクローリン展開によって美しく表現されます。
導出方法と一般形
テイラー展開の一般形は以下のように表されます:
\[ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x – a)^n \]
この式は、関数 \( f(x) \) の \( n \) 階微分 \( f^{(n)}(a) \) を用いて、その点 \( a \) のまわりで多項式的に近似していることを意味します。\( n! \) は \( n \) の階乗です。
代表的な関数の展開例
1. 指数関数 \( e^x \)(マクローリン展開)
\[ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \]
2. 正弦関数 \( \sin x \)
\[ \sin x = x – \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} – \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \]
3. 余弦関数 \( \cos x \)
\[ \cos x = 1 – \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} – \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \]
4. 自然対数 \( \ln(1 + x) \)(\(-1 < x \leq 1\))
\[ \ln(1 + x) = x – \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} – \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \]
応用:関数の近似や数値計算への応用
テイラー展開は、数値解析、物理学、工学など幅広い分野で使用されます。特に次のような場面で役立ちます:
- 複雑な関数を多項式で近似して計算を簡単にする
- 数値積分や常微分方程式の近似解
- コンピュータによる関数の計算(電卓やプログラムなど)
たとえば、\( \cos(0.1) \) を3次のマクローリン展開で近似すると:
\[ \cos(0.1) \approx 1 – \frac{(0.1)^2}{2!} + \frac{(0.1)^4}{4!} \approx 1 – 0.005 + 0.0000417 = 0.9950417 \]
実際の値 \( \cos(0.1) \approx 0.995004 \) に非常に近いことが分かります。
剰余項(誤差項)について
テイラー展開で切り捨てられる部分を「剰余項」または「誤差項」と呼びます。これを含めたテイラーの定理は次のように表されます:
\[ f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x – a)^n + R_N(x) \]
ここで、剰余項 \( R_N(x) \) は以下の形で与えられます(ラグランジュの剰余項):
\[ R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}(x – a)^{N+1},\quad a < \xi < x \]
この項によって、何次まで展開すればどれだけ近似できるかの精度が分かります。
まとめ
テイラー展開とマクローリン展開は、解析学の基本中の基本でありながら非常に奥深い概念です。関数を微分の情報から構成できるという直感的にも美しい構造を持っており、数学的にも応用的にも価値の高い道具です。これらを理解し使いこなすことで、関数の振る舞いをより深く捉えることができるでしょう。