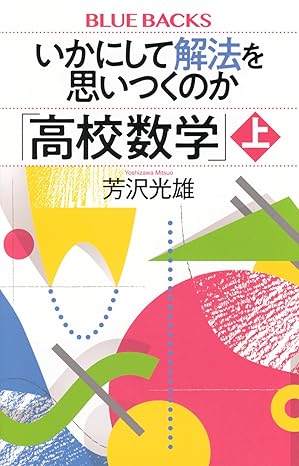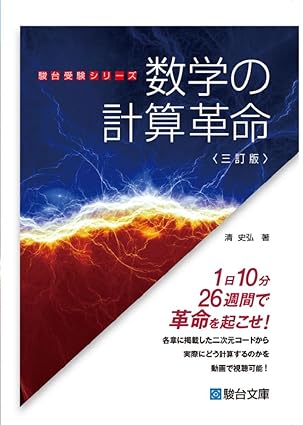アーベルの収束判定法:使い方と例題で理解
目次
- アーベルの収束判定法とは
- アーベルの定理(収束判定法)の定式化
- アーベルの定理の証明(概要)
- 例題1:交代級数への適用
- 例題2:べき級数との組み合わせ
- ディリクレの定理との関係
- アーベルの定理の応用例
- まとめ
アーベルの収束判定法とは
アーベルの収束判定法(Abelの定理)は、無限級数の収束を判定するための強力な手法の一つです。 特に、数列の項に交互符号や変化がある場合、または関数との積で表される級数の収束を調べたいときに有効です。 この定理は、19世紀の数学者ニールス・アーベルによって考案されました。
例えば、以下のような級数:
$$ \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n $$
に対して、どのような条件で収束するかを判断する指針を与えてくれます。
アーベルの定理(収束判定法)の定式化
アーベルの定理は以下のように表現されます:
アーベルの定理:
実数列 \\( \{a_n\} \\) および \\( \{b_n\} \\) に対して、
- 部分和 \\( A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \\) が有界である。
- 数列 \\( \{b_n\} \\) は単調であり、かつ収束する(有限の極限を持つ)。
このとき、積の級数
$$ \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n $$
は収束する。
アーベルの定理の証明(概要)
証明のアイデアは、部分和と単調性を活用して、和を評価することにあります。 基本的な考え方は、次のような恒等式を使うことです:
$$ \sum_{n=1}^{N} a_n b_n = A_N b_N – \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_{n+1} – b_n) $$
この恒等式から、\\( A_n \\) が有界であり、\\( b_n \\) が単調であれば、右辺の項が制御可能であるため、全体の和が収束することがわかります。
例題1:交代級数への適用
交代級数の一例として、
$$ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} $$
があります。これは有名な交代調和級数です。
ここで、\\( a_n = (-1)^n \\)、\\( b_n = 1/n \\)とすると、
- \\( A_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \\) は \\( \pm1 \\) で交互に振動するため有界。
- \\( b_n = 1/n \\) は単調減少で、0 に収束する。
したがって、アーベルの定理により収束が保証されます。
例題2:べき級数との組み合わせ
次に、べき級数との関係を見る例です:
$$ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (|x| < 1) $$
この級数が収束するとき、\\( x \to 1^- \\) の極限が存在するかどうかは、アーベルの定理を使って調べられます。
特に、部分和 \\( A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \\) が有界であれば、
$$ \lim_{x \to 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n $$
が成立します。これが「アーベルの連続性定理」とも呼ばれ、フーリエ級数などでも重要な役割を果たします。
ディリクレの定理との関係
アーベルの定理と密接に関連するもう一つの定理に「ディリクレの定理」があります。 こちらは、
- \\( \{a_n\} \\) は単調であり、0 に収束する。
- \\( \{b_n\} \\) の部分和 \\( B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k \\) が有界である。
という条件で、\\( \sum a_n b_n \\) の収束を保証するものです。 アーベルの定理と条件が逆になっていることに注目してください。
アーベルの定理の応用例
アーベルの定理は以下のような場面で応用されます:
- 交代級数や振動する級数の収束性調査
- フーリエ級数の境界収束性の評価
- 解析接続の理論における境界挙動の調査
- 漸近展開や擬級数の評価
まとめ
アーベルの収束判定法は、級数の収束を検討する際に極めて強力な手段となります。 特に、部分和が有界であり、もう一方の数列が単調かつ収束するという条件のもとで、その積の級数が収束することを保証します。
例題や他の定理(ディリクレの定理)との比較を通じて、より深く理解することができます。 解析学を学ぶうえでの基礎的かつ重要なツールであるため、確実に身につけておきたい知識の一つです。